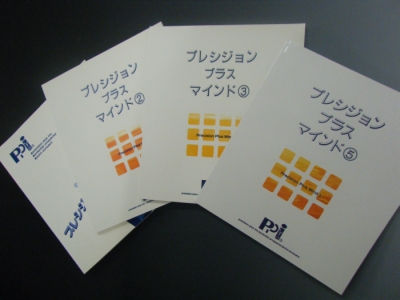技術開発の世界に身を置いている者としてはこんな感じ方が…。
***************************************
①ある定まった位置(現在の自己領域のテーマ)に立って、頭を四方八方へ巡らして何か無いかな、と。
②定点から一時的に踏み出して逍遥(何となくぶらぶら歩き)してみて…
③定点無しに何か、ひょっとして見つかるものがとの獲物を求める意識をもっての彷徨(さまよいうろつき)
***************************************
①では、運動暴発的行動なので余程の幸運(セレンディピティー)が無い限り糸口がつかめない。
②は、気分転換的行動型(犬も歩けば棒に当たる/兎飛び出す木の根っこ)なので、これも又難しい。
③さまよい中にピンと来る事象に当面したとき、定点を修正するか或は定点を新規に設定するか…。さまよいの運動量は大なれど獲物は大きい。
そこで、気分は②であるが、下心は③でゼミ・技術展・学会・技術・情報NET等を徘徊することに。ことに昨今は、かつて象牙の塔の主であった学者達がPRブースの店頭に立ってのセールス。これには、ポスターあり・プリントあり・丁寧なQ&Aトーク。
これらは、まさにデパート地下食品売場の如く、料理の種類は異なっていてもどれも美味しそう。自己の波長発信しての味見。レスポンス(反射)波長を感じながら脳の中でじっくり、ある時は瞬間的に問題が形作られる。能力開発に関わる知人曰く、それらは一応の技術知識の上に行動力・好奇心・先見能力・企画力がオンしている者のケースですよ…、と。